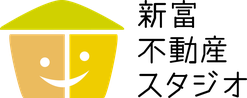マンション売却における注意点完全マスター

マンション売却は多くの選択肢と意思決定が必要な複雑なプロセスです。
「いつ売るべきか」「いくらで売り出すべきか」「どの不動産会社に依頼すべきか」など、一つひとつの判断が売却の成否を左右します。
「マンション売却における注意点完全マスター」は、そんなマンション売却のあらゆる場面で活用できる実践的なガイドです。
マンション売却経験が豊富な不動産のプロが、成功事例と失敗事例から導き出した重要な注意点を惜しみなく公開します。
この記事では、売却前の準備から価格設定のコツ、契約時の落とし穴、税金対策まで、売却の全過程で知っておくべき知識を体系的に解説しています。
これからマンション売却を考えている方はもちろん、すでに売却プロセスを進めている方も、ぜひチェックしてみてください。
マンション売却前に知っておくべき基本的な注意点
マンションを売却するという大きな決断をした後、多くの方が「どこから手をつければいいのか」「失敗しないためには何に気をつければいいのか」と不安を感じています。
実際、マンション売却は人生で何度も経験するものではないため、基本的な流れや注意点を知らないまま進めてしまうと、思わぬトラブルや損失につながることがあります。
ここでは、マンション売却を検討している方が最初に知っておくべき基本的な注意点について解説します。
マンション売却の全体的な流れと準備すべき書類
マンション売却は、「売却の準備」「不動産会社への依頼」「買主の募集と内覧」「価格交渉と契約」「決済と引き渡し」という5つの主なステップで進みます。
この流れを理解しておくことで、現在自分がどの段階にいるのかを把握し、次に何をすべきかの見通しが立てやすくなります。
売却準備の段階では、まず必要書類を揃えることが重要です。
特に「権利証(登記識別情報)」や「管理規約」「重要事項説明書」などは必要な書類となります。
これらの書類がない場合は再発行の手続きが必要で、時間がかかることもあるため、早めに確認しておきましょう。
権利証(登記識別情報)がない場合は所有権移転の際に本人確認情報等の有償の特別な手続きが必要となりますので、お早目に不動産会社へ伝えるようにしましょう。
また、マンションの管理費や修繕積立金の滞納がある場合は必ず清算しておく必要があります。
滞納があると売買契約の障害になることがあります。
そして、住宅ローンが残っている場合は、金融機関に完済予定であることを事前に連絡し、必要な手続きを確認しておくことも大切です。
不動産会社への依頼は、複数社に依頼するか、一社に専任で依頼するかを選択することになります。
一般的に広く買主を募るには複数社への依頼が有利ですが、手厚いサポートを受けるには専任媒介が適しています。
どちらを選ぶにしても、必ず媒介契約を結び、その内容をよく確認することが重要です。
内覧前には、マンション内の清掃や簡単な修繕を行い、良い印象を与えられるよう準備しましょう。
第一印象は購入判断に大きく影響します。
また、内覧時には個人情報が含まれる書類や貴重品は必ず片付けておくことが安全対策として必須です。
相場を知り適正価格を設定するための方法
マンション売却で最も重要な決断の一つが、売却価格の設定です。
高すぎれば買い手がつかず売却期間が長引き、安すぎれば損をしてしまいます。
適正な価格設定のためには、まず市場相場を正確に把握することが必要です。
相場を知るための方法としては、不動産ポータルサイトでの類似物件の価格チェック、不動産会社による査定、国土交通省が提供している「不動産取引価格情報」の閲覧などがあります。 特に査定については、必ず複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。
各社の査定額を比較することで、より正確な相場観が得られます。
また、マンションの価格に影響する主な要素として、「立地」「築年数」「階数・向き」「間取り・専有面積」「設備の状態」「管理状態」などがあります。
例えば、駅から徒歩10分以内の物件は需要が高く、高層階で眺望が良い物件も人気があります。
さらに、最近ではペット可のマンションや防犯設備が充実している物件の評価が高まっています。
売却価格を決める際には、これらの要素を総合的に考慮し、自分のマンションの強みと弱みを客観的に分析することが大切です。
そして、売り出し当初は少し高めの価格設定にしておき、反響を見ながら調整していくという戦略も一般的です。
ただし、あまりに高すぎる価格設定は、物件が市場に出てから時間が経つにつれて「何か問題がある物件ではないか」という悪印象を与えかねないため注意が必要です。
不動産会社選びで失敗しないためのポイント
マンション売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社選びが非常に重要です。
どんなに条件の良いマンションでも、不動産会社の営業力や販売戦略が不十分だと、希望通りの価格や期間での売却は難しくなります。
不動産会社を選ぶ際のポイントとしては、まずマンション売却に強い会社かどうか、そして「その地域での取引実績」が挙げられます。
マンションは土地や一戸建てなどとは違い、管理や長期修繕計画など様々な特殊要素がありますので、マンション売却の経験が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。
また 地域に精通している会社は、正確な相場観を持っていることが多く、適切なアドバイスが期待できます。
次に「営業担当者の対応の丁寧さ」も重要です。
質問への回答が迅速で分かりやすいか、こちらの要望をきちんと聞いてくれるかなどを確認しましょう。
そして、「販売戦略の具体性」も選定基準の一つです。
どのような層をターゲットに、どのような媒体で宣伝するのか、具体的な販売計画を提示してくれる会社が理想的です。
さらに「過去の成約事例」を確認することも有効です。
特に自分のマンションと似た条件の物件をどのくらいの期間・価格で売却できたかという実績は参考になります。
不動産会社との契約形態には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介は複数の会社に依頼できるメリットがありますが、各社の力の入れ方に差が出ることがあります。
専任媒介と専属専任媒介は一社のみに依頼する形ですが、特に専属専任媒介は不動産会社の責任が重くなるため、積極的な販売活動が期待できます。
契約前には必ず複数の不動産会社から話を聞き、査定額だけでなく、担当者との相性や会社の信頼性、販売力なども総合的に判断することをおすすめします。
高額な査定を提示する会社に飛びつくのではなく、その根拠をしっかり確認することも大切です。
マンション売却時によくあるトラブルと対処法
マンション売却は順調に進むケースばかりではなく、様々なトラブルが発生する可能性があります。
しかし、よくあるトラブルとその対処法を事前に知っておくことで、リスクを最小限に抑えることができます。
ここでは、マンション売却時に発生しやすいトラブルとその対処法について解説します。
売却価格を下げさせられるケースとその対策
マンション売却において最も多いトラブルの一つが、当初の予定より売却価格を下げざるを得なくなるケースです。
特に多いのが、不動産会社から「この価格なら売れる」と高めの査定額を提示されて契約したものの、実際に販売活動を始めると「市場の反応が悪いので値下げしましょう」と提案されるパターンです。
これはよくあるケースで、不動産会社が媒介契約を得るために高めの査定額を提示することがあります。
このような状況を避けるためには、契約前の査定額の根拠を具体的に確認することが重要です。
単に「この地域ではこのくらいです」という説明ではなく、同じマンションや近隣の類似物件がどのような価格で、どのくらいの期間で売れたのかという具体的なデータを示してもらいましょう。
また、媒介契約を結ぶ際には、値下げの条件や判断基準について事前に話し合っておくことも効果的です。
例えば「2ヶ月間は現状の価格で販売活動を続け、内覧が5件以上あっても成約に至らない場合は価格について再検討する」といった具体的な条件を設定しておくと良いでしょう。
さらに、売却急いでいるわけではない場合は、すぐに値下げに応じるのではなく、販売戦略の見直しを提案することも考えられます。
例えば、物件写真の撮り直しや広告文の見直し、内覧時の印象改善など、価格以外の面での対策も検討する価値があります。
買主からのクレームや契約キャンセルへの対応
買主が見つかり契約まで進んだとしても、その後にクレームが発生したり契約がキャンセルになったりすることがあります。
特に注意すべきは、引き渡し後に買主から「説明と違う」「不具合がある」などのクレームが出るケースです。
このようなトラブルを防ぐためには、物件の状態や設備の不具合について、事前に正確に伝えておくことが不可欠です。
例えば、「雨の日に窓枠から少し水が入ることがある」「エアコンの効きが悪くなっている」など、些細な不具合でも隠さずに伝えておくことで、引き渡し後のトラブルを防ぐことができます。
また、売買契約書には物件の現状や既知の不具合について明記しておくことも重要です。
書面に残しておくことで「聞いていない」というトラブルを避けられます。
特に築年数が経過したマンションの場合は、専門業者によるインスペクション(建物状況調査)を実施しておくと、客観的な物件状況が明確になり、買主との認識の差が生じにくくなります。
契約後のキャンセルについては、契約時に「手付金」の取り決めをしっかり行うことが対策になります。
一般的に、買主都合のキャンセルの場合は手付金を放棄することになりますが、その条件を明確にしておくことで、安易なキャンセルを防ぐことができます。
引き渡し時のトラブルを防ぐためのチェックリスト
マンション売却の最終段階である引き渡し時にもトラブルが発生することがあります。
主なトラブルとしては、「残置物の処理」「精算金額の相違」「引き渡し日の変更要請」などが挙げられます。
引き渡し時のトラブルを防ぐためには、まず売買契約時に引き渡し条件を明確にしておくことが重要です。
特に「どの家具・家電を残すか、撤去するか」「原状回復の範囲はどこまでか」「鍵や設備の取扱説明書などの引き継ぎ物」などについて、書面で確認しておきましょう。
また、引き渡し前には必ず物件の最終確認(ファイナルインスペクション)を行い、契約通りの状態になっているかを買主と一緒に確認することが大切です。
この際、水道やガス、電気などの各設備が正常に作動することも確認しておくと安心です。
引き渡し当日は、予定時間より余裕を持って現地に到着し、最終的な清掃状態のチェックや残置物の確認を行います。
そして、不動産会社や司法書士などの立会いのもとで、物件の引き渡しと同時に売買代金の決済を行うのが一般的です。
引き渡し後のトラブルを防ぐためには、引き渡し時の状態を写真に残しておくことも有効です。
万が一、後日「引き渡し時にはなかった傷がある」などのクレームがあった場合の証拠になります。
もし引き渡し後に買主から連絡があった場合は、まずは誠実に対応することが大切です。
些細な問題であれば迅速に対応し、大きな問題の場合は不動産会社や専門家に相談して適切に対処しましょう。
売主としての責任を果たすことで、トラブルの拡大を防ぐことができます。
マンション売却で損をしないための税金と費用の知識
マンション売却では、売却代金から様々な税金や費用が差し引かれます。
これらについて事前に正しく理解しておかないと、思ったよりも手元に残る金額が少なくなるというケースが少なくありません。
ここでは、マンション売却にかかる税金と費用について詳しく解説し、可能な限り負担を軽減する方法をご紹介します。
マンション売却にかかる税金の種類と計算方法
マンション売却で最も大きな税金となるのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。
取得費とは、マンションを購入した際の代金や諸費用、そして所有期間中のリフォーム費用などが含まれます。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や印紙税などが該当します。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって大きく異なります。
マンションを購入してから売却するまでの期間が5年以下の「短期譲渡」の場合、所得税と住民税を合わせて約39.63%という高い税率が適用されます。
一方、5年を超える「長期譲渡」の場合は約20.315%と税率が半分近くになります。
このため、可能であれば購入から5年以上経ってから売却するほうが税金面では有利です。
また、マンションを売却した年の1月1日時点での所有者に対して、その年の固定資産税と都市計画税が課税されます。
年間分をすでに支払っている場合は、売買契約時に買主との間で精算するのが一般的です。
さらに、売却代金が高額な場合は、復興特別所得税も課税されることがあります。
これは、東日本大震災からの復興財源を確保するために設けられた税金で、所得税額の2.1%が上乗せされます。
諸費用の内訳と相場を把握しておく重要性
マンション売却では税金以外にも様々な費用がかかります。
まず最も大きな費用となるのが「不動産仲介手数料」です。
これは売却価格に応じて上限額が法律で定められており、売却価格×3%+6万円(税別)が上限となります。
例えば3,000万円で売却した場合、最大で96万円(税別)が仲介手数料となります。
ただし、仲介会社によっては割引を行っているケースもあるため、事前に確認することをおすすめします。
次に「抵当権抹消費用」があります。
住宅ローンを完済し、抵当権を抹消するための費用で、司法書士報酬が1〜2万円程度、登録免許税が1,000円かかります。
また、売買契約書に貼付する「印紙税」も必要です。
売却価格に応じて金額が変わりますが、1,000万円〜5,000万円の場合は1万円、5,000万円〜1億円の場合は3万円となります。
引っ越し費用や、物件をきれいにするための「ハウスクリーニング費用」も忘れてはならない費用です。
専門業者によるハウスクリーニングは、一般的に5〜10万円程度かかります。
また、マンションの管理費や修繕積立金に滞納がある場合は、引き渡し前に全額精算する必要があります。
これらの費用を事前に把握し予算計画に組み込んでおくことで、「思ったより手元に残らなかった」という事態を避けることができます。
特に次の住居の購入資金に充てる予定がある場合は、正確な資金計画が重要になります。
特例措置や控除を活用して税負担を軽減する方法
マンション売却による税負担を軽減するためには、様々な特例措置や控除制度を活用することが効果的です。
特に重要なのが「3,000万円特別控除」です。
これは居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この特例を利用するためには、売却する物件に住んでいたこと、または住まなくなってから3年以内に売却することなどの条件があります。
また、「居住用財産の買い替え特例」も活用できる場合があります。
これは住んでいた家を売却し、新たに住む家を購入する場合に、譲渡所得への課税を繰り延べられる制度です。
一定の条件を満たせば、新居の取得価額から旧居の譲渡益を差し引くことができ、実質的に課税を先送りにできます。
さらに、マンションの売却で損失が生じた場合には「損益通算」や「繰越控除」という制度も利用できます。
これにより、他の所得と損失を相殺したり、最大3年間にわたって損失を繰り越して控除したりすることが可能です。
これらの特例や控除を適用するためには、確定申告が必要となる場合がほとんどです。
確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までに行います。
複雑な手続きになることが多いため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、2023年には「住宅ローン控除」の制度が改正され、中古住宅の購入も対象となるケースが増えました。
買主にとってのメリットが増えることで、中古マンション市場の活性化が期待されています。
このような最新の税制改正情報にも注目し、売却のタイミングを検討することも大切です。
マンション売却のタイミングと住み替え戦略
マンションを売却する際、「いつ売るべきか」というタイミングの問題と、「住み替えをどう進めるか」という戦略は非常に重要です。
特に現在住んでいるマンションを売却して新たな住居に移る場合、売却と購入のバランスを上手く取らなければ、一時的に住む場所がなくなったり、一度賃貸物件に引越したり、二重ローンを抱えたりするリスクがあります。
ここでは、適切な売却タイミングの見極め方や効果的な住み替え戦略について解説します。
売却と購入のタイミングをどう決めるべきか
マンション売却と次の住居の購入を同時に進める場合、大きく分けて「先に売ってから買う」「先に買ってから売る」「同時進行する」の3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
「先に売ってから買う」方法は、売却金額が確定するため次の住居の予算が立てやすいというメリットがあります。
また、住宅ローンの返済が終わるため、新しい住宅ローンの審査も通りやすくなります。
一方で、売却後から新居の引き渡しまでの間、一時的な住居が必要になるというデメリットがあります。
この場合、親族宅に身を寄せるか、賃貸住宅を短期で借りるなどの対応が必要です。
「先に買ってから売る」方法は、引っ越しを一度で済ませられる利便性がありますが、二重ローンのリスクを抱えることになります。
特に売却が予想より長引いた場合、経済的負担が大きくなる可能性があります。
この方法を選ぶ場合は、あらかじめ複数の不動産会社に自宅の査定を依頼し、売却の見通しを立てておくことが大切です。
また、「つなぎ融資」を利用して一時的な資金を調達する方法もあります。
「同時進行する」方法は、売却と購入の契約を同じ時期に行い、引き渡し日を合わせることで住み替えをスムーズに行う方法です。 理想的なのは、午前中に売却物件の引き渡しを行い、午後に新居の引き渡しを受けるという流れです。 ただし、双方の都合を合わせることが難しい場合もあるため、柔軟な対応が求められます。
不動産市場の動向も売却タイミングを決める重要な要素です。
一般的に春から夏にかけては転勤や入学シーズンで不動産取引が活発になる傾向があります。
また、金利動向や税制改正なども価格に影響するため、これらの情報もチェックしておくと良いでしょう。
内覧対策で印象を良くするための工夫
マンション売却を成功させるためには、内覧時に良い印象を与えることが非常に重要です。
内覧は買主が実際に物件を見る唯一の機会であり、この時の印象が購入判断を大きく左右します。
内覧対策の基本は「清潔感」「明るさ」「広さ」の3点です。
まず、マンション全体の徹底的な清掃は必須です。
特にキッチン、浴室、トイレなどの水回りは、わずかな汚れでも目立ちやすいため念入りに掃除しましょう。
カーテンを開け、すべての照明を点けることで明るい印象を与えることも効果的です。
また、部屋を広く見せるために、不要な家具や物を整理し、最小限の家具配置にすることをおすすめします。
特に廊下や玄関などの動線上には物を置かないようにし、スムーズに移動できるようにしておくことが大切です。
さらに、季節感を演出するための小さな工夫も効果的です。
例えば、リビングに季節の花を飾ったり、心地よい香りのアロマを焚いたりすることで、居心地の良さを感じてもらえます。
ただし、あまり強い香りは逆効果になることもあるため、控えめにすることがポイントです。
内覧時の温度管理も重要なポイントです。
夏は涼しく、冬は暖かく設定することで、快適に過ごせる住まいであることをアピールできます。
また、事前に窓を開けて換気をしておくことで、こもった空気や生活臭を軽減できます。
そして、内覧当日は可能な限り家族やペットは外出し、買主がゆっくり物件を見られる環境を作ることが理想的です。
どうしても在宅する必要がある場合は、必要以上に話しかけたり、付きまとったりせず、適度な距離を保つことが大切です。
住宅ローンが残っている場合の売却方法
多くの方がマンション購入時に住宅ローンを利用しており、売却を検討する時点でもローンが残っているケースが一般的です。
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、主に「完済型」「持ち出し型」「任意売却」の3つの方法があります。
「完済型」は、売却代金でローンを完済できるケースです。
売却価格がローン残高を上回っており、最も理想的なパターンです。
この場合、売買契約締結後に金融機関に連絡し、抵当権抹消の手続きを進めます。 決済日には、買主からの売却代金がいったん司法書士などに預けられ、そこからローンの残債が金融機関に支払われる流れになります。
「持ち出し型」は、売却価格がローン残高より低い場合で、その差額を自己資金で補填するパターンです。
例えば、ローン残高が2,000万円で売却価格が1,800万円の場合、差額の200万円を自己資金で用意する必要があります。
この方法は、早期に売却したい場合や、住み替えのために次の住宅購入を優先したい場合などに選択されます。
ただし、まとまった資金が必要になるため、資金計画をしっかり立てておく必要があります。
「任意売却」は、ローンの返済が困難になり、自力での返済が見込めない場合の最終手段です。
債権者(金融機関)の同意を得て、市場価格より安い価格でも売却する方法です。
競売よりは良い条件で売却できることが多いですが、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があるため、将来的な借入れに影響することを理解しておく必要があります。
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、まず金融機関に連絡して「ローン残高証明書」を取得します。
これにより正確なローン残高が分かり、売却価格設定の参考になります。
また、売却を前提としたローンの一部繰り上げ返済も検討する価値があります。
ローン残高を減らすことで、売却時の選択肢が広がる可能性があるためです。
新たな住居のためのローンを検討する際は、前のローンの返済状況が審査に影響します。
遅延なく返済を続けていれば、次のローンも組みやすくなります。
また、「財形住宅融資」や「親子リレー返済」など、年齢や収入に応じた特別なローン商品も視野に入れると良いでしょう。
まとめ
マンション売却は多くの人にとって人生の一大イベントであり、適切な知識と準備なしに進めると思わぬ損失やトラブルを招くことがあります。
本記事では、マンション売却における重要な注意点を幅広く解説してきました。
マンション売却を成功させるためには、まず基本的な流れと必要書類を理解し、適切な準備を行うことが大切です。
権利証や管理規約などの書類を早めに準備し、管理費や修繕積立金の滞納がないことを確認しておきましょう。
また、不動産会社選びは売却成功の鍵を握るので、実績や対応の丁寧さ、販売戦略の具体性などを総合的に判断して選ぶことが重要です。
売却価格の設定は、複数の不動産会社の査定を参考にしつつ、マンションの立地や状態、市場動向などを考慮して決定します。
高すぎる価格設定は売却期間の長期化につながり、安すぎる設定は損失を招くため、適正な価格設定が求められます。
売却時にはさまざまなトラブルが発生する可能性がありますが、事前に対策を講じておくことでリスクを軽減できます。
特に価格交渉や契約キャンセル、引き渡し時のトラブルなどは、明確な条件設定や丁寧なコミュニケーションによって防ぐことができます。
税金と費用に関する知識も不可欠です。
譲渡所得税の計算方法や、3,000万円特別控除などの特例措置を理解し、税負担を最小限に抑える工夫が必要です。
また、仲介手数料や抵当権抹消費用などの諸費用も事前に把握し、予算計画に組み込んでおくことが大切です。
住み替えを伴うマンション売却では、売却と購入のタイミングを慎重に検討する必要があります。
「先に売ってから買う」「先に買ってから売る」「同時進行する」のいずれの方法も、自身の状況や市場動向に合わせて選択することが重要です。
また、内覧時の印象を良くするための工夫も売却成功の重要な要素となります。
住宅ローンが残っている場合も、「完済型」「持ち出し型」「任意売却」など状況に応じた選択肢があります。
ローン残高証明書を取得し、正確な残高を把握した上で、最適な方法を選ぶことが大切です。
マンション売却は一筋縄ではいかない複雑なプロセスですが、本記事で解説した注意点を押さえておくことで、失敗やトラブルのリスクを大幅に減らすことができます。
事前の準備と知識が、スムーズで満足のいくマンション売却の鍵となるでしょう。
最後に強調しておきたいのは、マンション売却においては「情報収集」と「専門家への相談」が非常に重要だということです。
不動産市場や法律、税制は常に変化しているため、最新の情報を収集し、必要に応じて不動産の専門家や税理士などのアドバイスを受けることで、より確実な売却を実現できます。
皆様のマンション売却が成功し、次のステップへのスムーズな移行ができることを願っています。
マンション売却に関するよくある質問(Q&A)
Q1: マンションを売却する際、リフォームをした方が良いのでしょうか?
A1: マンション売却前のリフォームは、費用対効果をしっかり考慮する必要があります。
基本的には、大規模なリフォームよりも、清掃や簡単な修繕、壁紙の張替えなど、費用を抑えた「クリーニング」レベルの対応がおすすめです。
水回りの設備が古い場合でも、全面的な交換よりも、シャワーヘッドの交換や蛇口のパッキン交換など、最小限の修繕にとどめるのが賢明です。
ただし、明らかな不具合や破損がある場合は修繕しておかないと、内覧時の印象が悪くなるだけでなく、売却価格の値下げ交渉の材料にされる可能性があります。
また、リフォーム費用は確定申告で「取得費」に算入できるケースがあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
売却前のリフォームについては、不動産会社に相談し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
Q2: マンション売却時の「仲介手数料」と「買取」の違いは何ですか?どちらがお得なのでしょうか?
A2: 「仲介」と「買取」はマンション売却の代表的な二つの方法で、それぞれ特徴が異なります。
仲介の場合は、不動産会社が売主と買主の間に立って売買を成立させるサービスです。
仲介手数料が発生しますが(売却価格の3%+6万円+税が上限)、市場価格で売却できる可能性が高く、高値での売却を目指す場合は仲介がおすすめです。
一方、買取は不動産会社が直接マンションを購入するサービスです。
仲介手数料はかからず、売却が確実で手続きも迅速ですが、通常は市場価格より2〜3割低い価格での売却となります。
急いで現金化したい場合や、リフォームが必要な物件、相続した遠方の物件などは買取が適している場合があります。
どちらがお得かは一概には言えず、売却の急ぎ具合、物件の状態、希望する売却価格などを総合的に考慮して選ぶべきでしょう。
不安な場合は、まず仲介で売り出し、一定期間内に売れなければ買取も検討するというアプローチも有効です。
Q3: マンションを相続した場合の売却における特有の注意点はありますか?
A3: 相続したマンションを売却する場合、通常の売却とは異なる特有の注意点がいくつかあります。
まず最優先で行うべきは「相続登記」です。
相続したマンションの名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きで、これが完了していないと売却できません。
法務局で行う手続きですが、複雑な場合は司法書士への依頼をおすすめします。
次に「相続税」と「譲渡所得税」の関係を理解しておく必要があります。
相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、「取得費加算の特例」が適用できる可能性があります。
これは、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度で、譲渡所得税の負担軽減につながります。
また、相続したマンションの「取得費」の計算方法も重要です。
購入時の価格が不明な場合は「概算取得費」として、売却価格の5%を取得費とすることができます。
ただし、実際の取得費がわかる場合はそちらを使用した方が有利なケースが多いため、被相続人の書類をできるだけ探しておくことをおすすめします。
相続したマンションに被相続人の家財道具が残っている場合は、売却前に整理する必要があります。
遺品整理は専門業者に依頼することも可能です。
また、管理費や修繕積立金の滞納がないか、固定資産税の支払い状況なども確認しておきましょう。
相続したマンションを複数人で共有している場合は、売却するには共有者全員の同意が必要です。
意見がまとまらない場合は「共有物分割請求」という法的手段もありますが、できるだけ話し合いでの解決が望ましいでしょう。